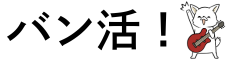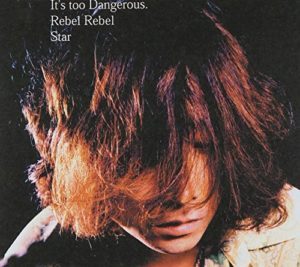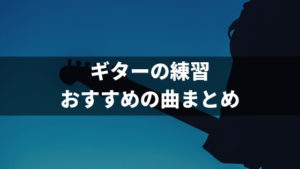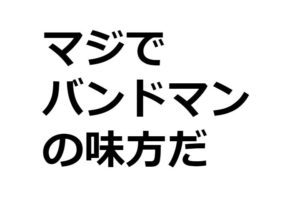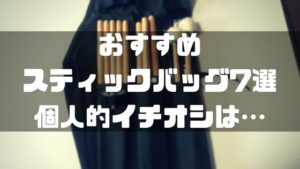音楽プロモーション/マーケティング事例20選。バズる施策の共通点とは!?

音楽をどう広めるか──これはインディーズでもメジャーでも永遠のテーマです。
いくら曲が良くても、ただ配信して待っているだけでは届かない。
だからこそ「ファンが集まれる場所」や「ちょっとした驚き」「今っぽい仕掛け」が効いてきます。
この記事では、BUMP OF CHICKENのアプリやGLAYの会員制サービス、GU×Spotify×imaseのコラボ、ハイスタやRadioheadのサプライズ施策など、国内外の音楽プロモーション事例をまとめました。
あなたの活動にそのまま取り入れられるヒント、きっと見つかるはずです!
スケールが大きい!メジャー音楽アーティストのマーケティング事例
まずはメジャーで活躍する人気アーティストの事例です。
GU×Spotify×imaseの“聴けるTシャツ”——音楽×ファッションで広がる導線
GUとSpotifyが新世代アーティスト・imaseとコラボし、楽曲ジャケットをモチーフにしたTシャツや小物を2025年5月16日に発売。
アイテムにはSpotifyコードが付き、読み取るだけで「This Is imase」プレイリストへアクセスできる“聴けるTシャツ”になっていました。
日本に加え台湾・香港・中国・米国でも展開し、渋谷・新宿フラッグス・NYソーホー店では特別ディスプレイも。
音源への導線をグッズや名刺、フライヤーにQR/Spotifyコードとして仕込む発想は参考になります。
音楽への入口は音源そのもの以外にも作れる事例です。
imaseは「NIGHT DANCER」でTikTok発のヒットを獲得し、Spotifyバイラルで世界各国トップ50入り、23・24年は「海外で最も再生された日本の楽曲」TOP5入りするなど実績を持つアーティスト。
この事例は、Tシャツやトートを“着てもらう広告塔”にし、音楽×ファッションの掛け算でリーチを拡張する好例でした
YELLOW MONKEYが独自アプリで聞き放題を実施
イエモンは2016年の再結成にあわせて、独自アプリを立ち上げ、月額400円で楽曲が聴き放題になる仕組みを導入しました。
一般的なストリーミングサービスではアーティストがファンと直接つながることが難しいですが、独自アプリにすることでコンテンツ配信やチケットトレードなどを実現し、ファンとの接点を確保しています。
収益性や顧客接点というストリーミングの弱点を克服した好例であり、インディーズや個人でもnoteなどのプラットフォームを使えば応用できるモデルです。
※現在はライブ映像見放題の「TYM STORAGE」としてリニューアルしています。
【イエモンの進化版?】GLAYのアプリ
GLAYも2017年より月額1,000円で使える公式アプリを出していて、曲やMV、過去のライブ映像まで全部見放題・聴き放題にしています。
最新情報や会報誌まで配信されるので、ほぼ“スマホの中にファンクラブ”があるようなイメージです。
普通のストリーミングだとアーティスト側はファンに直接アプローチできませんが、独自アプリならコンテンツもファンとのつながりも自分の手の中に置けます。これはまさに「自分たちのプラットフォームを持つ」やり方です。
インディーズや個人で同じ規模のアプリは難しいけれど、noteの月額マガジンや会員制のサイトを使えば近いことは十分できます。
大手プラットフォームでまず知ってもらい、その後は自分の場所にファンを招く、という流れを意識すると参考になります。
ミュージシャン公式アプリの完成形?BUMP OF CHICKEN「be there」
BUMP OF CHICKENの公式アプリ「be there」(2023年公開)は、情報を流すだけでなく、ファンが“いつでも戻ってこられる場所”をつくる発想で作られています。
核になっているのは、楽曲が24時間流れ続けて、聴いている人同士がリアクションでゆるくつながれる「LIVE MUSIC」。
SNSほど騒がしくなく、ライブほどハードルも高くない、心地いい待ち合わせ場所のような機能です。
もう一つのポイントは、藤原基央さんのキャラクター「ニコル」。本人そのものではなく“もう一つの人格”を通して交流できるので、世界観に入りやすく、距離感も優しく保てます。
さらに、毎年のデジタル会員証や、ここだけの映像・インタビュー・限定グッズが用意され、コアファンが長く楽しめる導線がきちんと設計されています。
背景には、コロナ禍で「会えなくても、一緒にいられる場所をつくりたい」という動機がありました。
要するに、「いつ行っても誰かがいて、あなたの音楽が鳴っている場所」を用意すること。
そこに世界観の入口と、ちょっと特別なお楽しみを添えること。
インターネットへの常時接続が当たり前になった今に即した、ミュージシャンアプリの最新事例と言えます。


人気バンドだからこそ素晴らしい提案をしたLUNA SEA
LUNA SEAは2017年5月の日本武道館公演で、燃料電池車の電力だけでライブを実施し大きな話題を呼びました。
エコで社会的意義があるだけでなく、「音質が良くなる」という効果まで期待される取り組みです。
しかも、この試みは経済ニュースにも取り上げられ、普段音楽ニュースを見ない層にまで届いたのがポイントでした。
単なる環境アピールにとどまらず、社会貢献 × 宣伝効果 × バンドのブランディングが同時に成立している好例です。
規模は違っても、インディーズでもクラウドファンディングなどで「三方良し」の企画を意識すれば、共感を得やすく成功につながりやすいでしょう。
いつも最新のマーケティングをするRadiohead
Radioheadは9thアルバム『A Moon Shaped Pool』のリリース時に、ネットから公式情報を一時的に消す → ファンに謎のポストカードが届く → SNSで情報を小出し → MV公開 → 特設サイトで一気に発売という流れを取りました。
わずか1週間のスピード感で展開したのがポイントです。
テレビや雑誌に頼らず、SNSとファンの熱量だけで大きな話題を作り、しかも販売も自分たちの特設サイト経由。つまり、マスメディアに頼らない宣伝 × 既存流通に頼らない販売を実現していたわけです。
規模は違っても、「SNSで話題を仕掛ける」「BASEを使ってすぐ販売する」というのはインディーズでも応用可能。たとえば「昨日のライブ音源をすぐ配信!」みたいなスピード感ある動きは、個人でも取り入れられる戦略です。
ちなみにRadioheadは2025年に7年ぶりのライブを開催することをフライヤーのみで先行公開しました。
やはりいつの時代も驚きを与えてくれる存在です。
BTS JINのサブスク再生キャンペーン
BTS・JINのセカンドソロ『Echo』収録曲「Don’t Say You Love Me」を対象に、ユニバーサルがLINE MUSICで再生キャンペーンを実施。
期間内に曲をたくさん聴き、アプリの「Your Play TOP 50」のスクリーンショットを応募フォームから送ると、未公開フォトカードが抽選でもらえる――という、とてもシンプルな設計です。
参加のハードルが低く、実再生の証跡も取れ、限定特典が動機づけになるため、再生数と話題化を同時に伸ばせます。
このような再生キャンペーンは今は多くのアーティストで行われています。
「聴く」という日常行動を、そのまま“関われる体験”に変換。
同時にバイラルチャートに露出することで、さらに認知を拡大できる強力なキャンペーンと言えます。
“食べる音”をサンプリングして話題作りに成功したカルビーの音楽レーベル
カルビーが音楽レーベル「じゃがレコード」を設立し、第1弾『DAHA』をリリース。
ポテトチップスの“パリッ”“ザクザクッ”という咀嚼音をパーカッションに使い、疾走感のある楽曲とアニメーションMVで話題化しています。
制作はniKu(Chinozo × がちゃ)、ゲストVoにTHE BINARYのmido。2025年4月29日配信開始、主要ストリーミングとYouTubeで聴け、JOYSOUNDでも6/12から歌唱可能。
タイアップ色よりも“音の遊び”を前面に出し、企画性と音楽性を両立させているのがポイントです。
スマホ録音の生活音でも十分にサンプリング素材になるし、食や日常行動など共感しやすい題材はSNS拡散と相性が良いでしょう。
短尺動画(TikTok/ショート)とMVを連動させ、“日常を音楽に変える”切り口で話題導線を作れます。
これはインディーズでも十分に再現できる事例だと思います。
音楽ビジネスのニュースタンダードモデルを提示したチャンスザラッパー
2017年に「最も稼いだ音楽アーティスト」になったチャンス・ザ・ラッパーは音源を有料販売せずに無料配信/ストリーミング中心で広め、そのぶんグッズ(特にツアー限定など)と企業コラボでしっかり稼ぐモデルを確立しました。
Apple Musicの独占配信など“プラットフォームとの提携”で話題と収益を同時に作り、最終的にはグラミー受賞まで到達。
今日ではスタンダードになった「CDに頼らない稼ぎ方」のロールモデルになったケースです。
インディーズでも、もちろん応用可能。
まずはYouTube/TikTok等で無料で広げる → TUNECOREなど音楽配信代行サービスでサブスクに流す → 自分のショップ(BASE等)でグッズを展開、さらに地元企業との小さなスポンサードも可能性があります。
作品を“入口”にして、ファンが欲しがるモノ/体験で収益化する発想がポイントです。


斬新で話題を呼んだインディーズ音楽アーティストのマーケティング事例
続いて、インディーズで独自のセンスでバズったマーケティングをご紹介します。
メジャーほど予算はないのでスケールは小さくなるものの、アイディアが光る事例が並びました。
いつの時代もカッコいいハイスタのマーケティング
Hi-STANDARDは2016年当時、16年ぶりの復帰作でサプライズ連発。
告知ゼロでシングルCDをゲリラ発売→全国のアナログ看板でアルバム告知→駅に巨大バンドスコア掲示→コンビニ印刷で誰でも楽譜ゲット→発売日に過去フェスのサプライズDVD→さらに「誰かに渡してね」と一枚プレゼントできるギフトCD…という流れで、“Gift”のテーマを一貫して実行。
結果、コアファンが自発的にSNSで拡散し、話題が雪だるま式に膨らみました。
学べるポイントは、
- コアファンが本当に喜ぶ体験を設計(店舗・楽譜・贈る仕掛けなど手触りのある要素)
- オフラインで驚かせて→オンラインで広がる導線を作ること。
規模は小さくても、あなたの現場でも「手渡しの特典」「地元掲示×SNSハッシュタグ」「ライブ当日のサプライズ配布」などで、同じ思想は十分に再現できます
メジャーと提携、という在り方
感覚ピエロは、レーベルに所属せず自分たちで運営を回すDIYスタイルで活動してきたバンド。
ドラマ主題歌に抜擢されるなど実力も評価される中、ついに自主レーベルを株式会社JIJIとして法人化し、エイベックスから出資を受けるというニュースで話題になりました。
従来の「メジャーデビュー=大きな会社に所属」という形ではなく、自ら会社を立ち上げてメジャーから出資を受ける=間接的なメジャーデビューとも言えるスタイル。
これは「レーベル型」から「プロジェクト型」へと移行している音楽業界の象徴的な出来事です。
インディーズ目線で学べるのは、主体性を持って活動を組み立てる力の重要性。
時代的にも「大企業に守られる」より「自分でチームを作る」方向へ進んでいます。
感覚ピエロのように、自分のやり方を会社や形に落とし込みながら進めることが、これからのミュージシャンにとって大切なヒントになるでしょう。
地域に根差した音楽ビジネス
仙台拠点の株式会社劇団ニホンジンプロジェクトは、演者=社員・社員=演者という体制で、会社員ミュージシャンとして活動。
職業ソング/企業ソング/オリジナル楽曲など企画を量産し、地道な販売と手売りまで積み上げて、最大8000人動員のアリーナ公演を達成。
“レーベルに所属する”ではなく、自分たちで事業を作って育てるモデルで成果を出した好例です。
- 企画を分散:オリジナルだけでなく職業ソング・企業タイアップなど複線化して収益源を増やす
- 役割の内製化:メンバーが制作+営業+広報まで分担し、スピードと実行力を上げる
- ローカル徹底:地元密着のPRと手売りで“確実に来るお客さん”を積み上げる(認知<人気・熱量)
ちなみに主要メンバーだったさくまさんは現在、音楽系YouTuber MELOGAPPAとして活躍しています。
独立して活動するプライベーター音楽アーティストのマーケティング事例
プライベーターとは、音楽事務所やレーベルに所属せず個人として活動する形態のこと。
音源のリリースが誰でも簡単にできるようになった現代では、多くのミュージシャンがプライベーターとして活躍しています。
以下ではそんなプライベーターのミュージシャンが実践している個人レベルでできるマーケティング事例をご紹介します。
Spotify経由で海外からヒットが逆輸入されたAmPm
覆面ユニットAmPmは、デビュー曲をSpotify中心に展開してバイラル入り→数百万〜千万回規模の再生へ。
レーベル所属なしでも、プレイリスト露出×継続リリースで世界に届くことを証明した代表例でした。
メンバーはマーケ/デザインの知見を持ち、広告やキュレーター起点の拡散を“設計”しているのがポイントです。
- リリース初月は少額広告+プレイリスト向けのピッチで初速を作る(規約と倫理は順守)
- 短いサイクルで単曲リリース→バイラルの波に乗りやすくする
- 海外も視野に英語タイトル/タグ/説明を整備。アートワークの統一感で覚えてもらう
- Spotify for Artistsで事前ピッチ、Canvas、プリセーブ活用。聴かれた国・都市を見て次の打ち手を決める
- コラボ(客演・Remix)で別オーディエンスへ横展開


多角的な活動をするモモモリメイさん
シンガーソングライターのモモモリメイさんは、クラウドファンディングで73人から約44万円を集め、さらにワンマンライブを成功させた実績を持っています。
その背景には、地道で継続的な発信活動がありました。
たとえば「一曲一会」と題して毎週新曲をTwitter(現 X)に公開し、その後YouTubeにも展開。
火曜日にはツイキャスで生配信を行い、ほぼ毎日ブログを更新して活動を記録するなど、音楽だけでなく日常的にコンテンツを届け続けています。
イラストレーターとコラボしたミュージックビデオの制作なども含め、積み重ねた努力がクラウドファンディングやワンマン成功につながったと言えるでしょう。
インディーズミュージシャンにとって、この事例から学べるのは「定期的にテーマを決めて発信し、継続すること」が信用を生み、ライブ動員や支援に直結するという点です。
ミニクラウドファンディングを使った音源リリースを試したハヤシユウさん
シンガーソングライターのハヤシユウさんは、新作「Summer Slumber」を通常の販売だけでなく、フレンドファンディングアプリPolcaを使ってリリースしました。
Polcaを通じて購入すると、本人からメッセージが届いたり、他の購入者が見える仕組みがあり、まるでライブハウスの物販のような「交流感」を楽しめるのが特徴でした(※Polcaはすでにサービス終了)。
さらに彼は以前、楽曲「ワンダーランド」をフリーBGMサイトに登録。
その音源が人気YouTuberの動画で使われたことで一気に再生数が伸び、音源リリースへとつながった実績があります。
この流れは「音源を公開→誰かに使ってもらう→大きな拡散につながる」という好例で、バンドマンにも応用できる戦略です。
音源を売る方法はCDや配信だけではなく、クラウドファンディングやフリーBGMとして公開するなど、人に使ってもらうことで広がる可能性もあることを示してくれました。
プライベーターの先駆け 二人組ユニット
「日本一ハンバーガーを愛するアーティスト」をキャッチコピーに活動していたデュオ Sleepyhead Jaimie。
楽曲やツアーのテーマを「ハンバーガー」に統一し、わかりやすいコンセプトでブランディングを確立しました。
活動の中心は、全国のハンバーガーショップを回るツアー。
チケット代は設定せず投げ銭制とし、さらにグッズやCDをライブ物販だけでなく自前のウェブショップでも販売して収益化。
YouTubeやブログも積極的に活用し、広告収入やネット投げ銭といった仕組みも取り入れていました。
大きな特徴は、経済的観念を持ちつつ行動力と編集力を兼ね備えていたこと。
クラウドファンディングでキャンピングカーを購入し、全国を回るという挑戦を実現。
その過程をブログや動画で発信し続けることで、音楽活動そのものを魅力的なコンテンツに変えていました。
「テーマを明確に打ち出すこと」「収益の仕組みを自分で作ること」「発信を継続すること」――この3点が、プライベーターミュージシャンが学べる大きなポイントです。

プライベーターの先駆け コンポーザー×2
作曲家のこおろぎさんは、事務所に所属せずに月20万円前後を安定して確保。
受託制作に加え、オーディオストックやブログ広告などの“ロングテール収入”を組み合わせ、収入を分散させています。
一方のまつきあゆむさんは、自分の楽曲を自分のサイトで直接販売するスタイル。
Bandcampのような仕組みを活用し、作品と世界観を一体で発信しています。
共通するのは、自前のチャネルを持ち、複数の収入源でリスクを分散すること。
2020年以前にプラットフォームに依存せず「音楽で食べていく」ための現実的なヒントを提案した二人の事例です。
メンバー内シェアハウス
知的風ロックバンド mothercoat は、2015年当時、埼玉の「凡人ハウス」と呼ばれるシェアハウスでメンバーと共同生活。
自宅にスタジオを構え、畑で育てた野菜まで物販で売るユニークな活動スタイルが特徴です。
大きな固定費を抑えつつ、国内外のライブやフェスへ出演。ギャラも「東京で2万円+交通費」と明確にし、安売りせずに自分たちの価値を示しています。
柔軟な発想と生活と音楽を融合させたスタイルは、「音楽で食べる」ことを模索するミュージシャンにとって新しいヒントになりました。
プライベーターとして活躍する数少ないロックバンド
ロックバンド Yellow Studs は大手に頼らず、自主レーベルで活動を展開。
インディーズファンを中心に全国的な知名度を得ながらも、完全DIYで運営を続けています。
特徴的なのは、自らのレーベルを立ち上げ、作品制作から営業・流通までを自分たちで管理していること。
公式YouTubeには多数の高品質なMVを公開し、定期的にアルバムをリリース。
さらに公式サイトや自前のショップを整え、グッズ販売やファンとの直接的なつながりも大切にしています。
「一生音楽を続けるなら、自分の力で活動できる仕組みを持て」という姿勢は、多くのバンドにとって現実的なロールモデルとなっています。
CDをSNS拡散のネタに
2018年新宿ANTIKNOCKで開催されたイベント「SAD COMMUNICATION」では、来場者が指定ハッシュタグ付きでSNS投稿すると、その日の出演バンドを1曲ずつ収録したオムニバスCDを“無料”で配布する施策を実施。
結果は約120人の来場中、ちょうど100人がCDを受け取り、ツイッターを中心に多くの投稿がタイムラインで可視化されました。
ライブに間に合わずCDだけ取りに来た人もおり、「無料+投稿インセンティブ」による集客・拡散効果が確認できた形です。
複数バンドを束ねた“コンピ”は相互にファン層へ届きやすく、SNS上の話題化も促進。
主催側がプレス費や会場費の一部を負担し、出演者の負担感を下げた点も好印象でした。
総じて、ライブ体験と持ち帰り価値をセットにし、投稿条件でUGCを生むシンプルな設計が成功要因。
バンドやイベント主催者にとって、再現性の高いプロモーション事例と言えます。
成功する音楽プロモーションの3つの共通点
これらのプロモーション・マーケティング事例から、以下の共通点が見えてきました。
音楽活動を続けていくうえで、大きなヒントになります。
① ファンコミュニティがある
BUMP「be there」やGLAYの公式アプリ、そして各種クラウドファンディングの成功は、強いファンコミュニティに支えられています。
もちろん核にあるのは“音楽の魅力”。
卵が先か鶏が先か、という話ではありますが、少なくともファンが集まれる「居場所」を用意しなければ、コミュニティは育ちにくい。
まずはLINEやメルマガといった小さな母艦を立ち上げ、限定視聴や裏話を継続して届ける――その“直接つながる導線”こそが、発信を点から面へ広げ、音楽活動の土台になります。
② 驚きがある
Hi-STANDARDのゲリラ発売や、Radioheadの“ネットから消えて一気に解禁”は、オフラインの驚きをオンラインで可視化する設計が巧みでした。
告知→発売の一本道を外れ、当日だけの未告知特典や、沈黙からの一斉公開といった温度差を作ると、ファンは自発的に語りたくなります。
手触りのある体験をきっかけに、SNSでの共有が自然発生する流れを狙うのがコツです。
③ トレンド性がある
LUNA SEAの水素エネルギーライブのように社会的トピックと接続すると、音楽ニュース外の層にも届きます
GU×Spotify×imaseの“聴けるTシャツ”、カルビー「じゃがレコード」の“食べる音サンプリング”、JINのサブスク再生キャンペーンも、いまの消費行動やメディア環境に寄り添った打ち手でした。
グッズやフライヤーから即試聴に飛べる導線や、短尺動画・再生企画でアルゴリズムに乗る工夫は、規模に関係なく再現できます。
以上のように
- 居場所(関係)
- 驚き(体験)
- 今(文脈)
がそろうほど、プロモーションは強く、長く効きます。
アマチュアからインディーズミュージシャンが自分でプロモーションを考える際も、ぜひ参考にしてみてください。