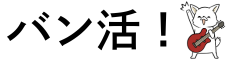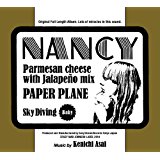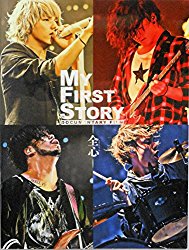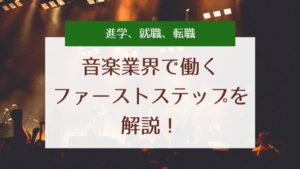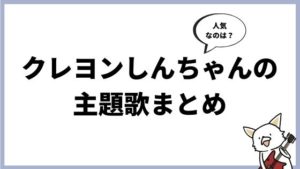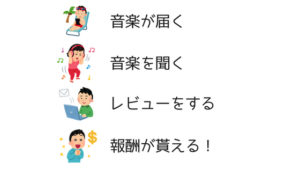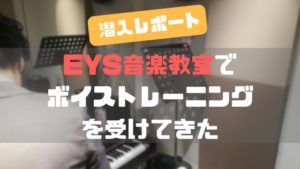個人でネットラジオを始めるなら?失敗と成功から学ぶ6ステップ&サービス比較

「個人でもネットラジオを始められるの?」
わたしは以前、バンド活動の一環でPodcastを利用してネットラジオ番組を配信していました。
なんどか配信して、好評で成功だった回もあれば失敗だった回も。
この記事では、そんな実体験に基づくネットラジオ(音声配信)の始め方を6ステップで解説。
さらに、主要配信サービスの比較とおすすめアプリ、Podcastにも同時配信する方法、続けるためのコツまで紹介します。
これから配信を始めたい方にとって、失敗談も含めたリアルな情報をお届けします!
ネットラジオ(音声配信)の始め方|6ステップ
1. テーマとターゲットを決めよう
音声配信を始める前に、「何を話すのか」「誰に届けたいのか」を決めましょう。
例えば、ミュージシャンなら「ライブの裏話」「楽曲制作の過程」「好きな音楽の紹介」などがテーマになります。
ターゲットも明確にすると内容のブレがなくなります。「ファン向け」「同業ミュージシャン向け」「趣味仲間向け」など、聞く人を想定して話すと、親近感のある番組になります。
2. 配信方法を決めよう
音声配信には大きく分けて2つの方法があります。
- Podcast
Apple PodcastやSpotifyなど、複数の配信先に自動的に配信できる仕組みです。世界中からリスナーを獲得しやすい反面、録音や編集、RSS設定など少し手間がかかります。 - 音声配信アプリ(stand.fm・Radiotalkなど)
スマホ1台で録音〜編集〜配信まで完結。操作がシンプルで、初心者にも始めやすいのが特徴です。
stand.fm・Radiotalkは設定すればPodcastにも同時配信可能なので、「まずアプリで簡単に始めたいけど、後でPodcastでも聞けるようにしたい」という人に向いています。(詳しくは後述)
3. 機材を準備しよう(スマホ+マイクでOK)
スマホ内蔵マイクでも十分配信できますが、より聞きやすい音にするなら外付けマイクを使います。
3,000〜5,000円程度のUSBコンデンサーマイクや、有線イヤホンマイクがあれば、ノイズが減って音質が格段に上がります。
4. 収録場所を準備しよう
音声のクリアさは環境で大きく変わります。
自宅の静かな部屋、音楽スタジオがおすすめ。
エアコンや換気扇の音はオフにし、反響を抑えるためにカーテンやクッションを活用するとプロっぽい仕上がりになります。
5. 録音〜編集〜配信
stand.fmやRadiotalkでは、アプリ内で録音・カット編集・BGM挿入・配信までできます。
Podcast配信をしたい場合は、stand.fmの「Podcast連携」やSpotifyに「Spotify for Creaters」を使うと、複数のプラットフォームに自動配信できます。
6. 継続して発信&リスナーと交流
配信は一度で終わらせず、週1回など自分が続けやすいペースで更新しましょう。
コメントやメッセージ機能を使ってリスナーとやり取りすると、番組に親しみを持ってもらえます。
継続と交流は、リスナーの定着に欠かせません。
始めてしまえばカンタンです!
個人がネットラジオをはじめるならStand FMがおすすめ
【比較表】ネットラジオ開局サービス3選
| サービス名 | 特徴・配信形式 | 料金 | 初心者向け度 |
|---|---|---|---|
| Stand FM | 収録・編集 ラジオ配信 ライブ配信 Podcast連携 収益化 | 無料 | ★★★★★ |
| Radiotalk | 収録・編集 ラジオ配信 ライブ配信 Podcast連携 収益化 ※ラジオ上限12分 | 無料 | ★★★★☆ |
| Podcast | 別ソフトで収録・編集が必要 Spotify for Creatersなど配信サービスを利用 | 無料 | ★★★☆☆ |
Stand FMをおすすめする理由
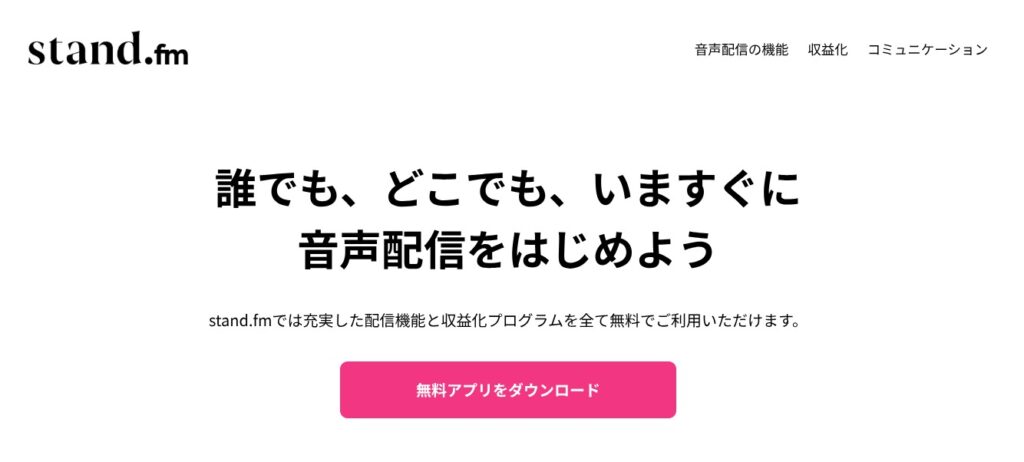
ネットラジオをはじめるには、
- ラジオ配信アプリ(Stand FM・Radiotalk )を使う
- なんらかのソフトで音声を収録・編集 → Podcastに配信する
といった2つのパターンがあります。
おすすめはラジオ配信アプリを使った方法です。
特にStand FMをおすすめします。
- リスナーとの交流機能が標準装備 → コメントや質問が直接届くため、別サービスを使わなくていい。
- 録音・編集・配信がアプリ内で完結 → 外部ソフト不要。スマホだけでプロセスが終わる。
- 配信先の自動連携がある → Podcast配信をしたい場合も1回設定すればOK。
アプリ内の収録・編集以外にも、PCから収録済みの音源をアップロードすることも可能。
なので、より本格的に編集した音声も配信可能です。
Radiotalkもほとんど同じ機能を揃えていますが、ラジオの上限が12分まで。
12分はやや短いかと思うので、ここではStand FMをおすすめしたいと思います。
Stand FMからPodcastに配信しよう
Stand FMで配信したラジオをPodcastとして、
- Spotify
- Apple Muisc
- Amazon Music
- YouTube
など人気アプリ内で配信することが可能です。
特にミュージシャンのラジオの場合、音楽アプリで配信しない手はないので、ぜひPodcast配信の設定をして下さい。
Stand FMで配信した後に、設定されたRSSフィード(URL)をそれぞれのアプリに登録します。
詳しくはStand FMのヘルプページを参照して下さい。
Stand FM → Podcastが最もカンタンかつ間口が広い!
【経験談】ネットラジオ番組づくりのポイントを紹介
実はわたし自身も以前のバンド活動でPodcastを利用してネットラジオ番組を配信していました。
参考:Rundaban Spoiler Party podcast「どうなっちゃってんだ」
以下ではその経験で気づいたネットラジオのコツをご紹介します。
もちろん、プロではないので高度なノウハウではありませんが、逆に「これからはじめよう!」という方には参考になると思うので、ぜひご覧ください。
トークに自信がない人はBGMを入れよう
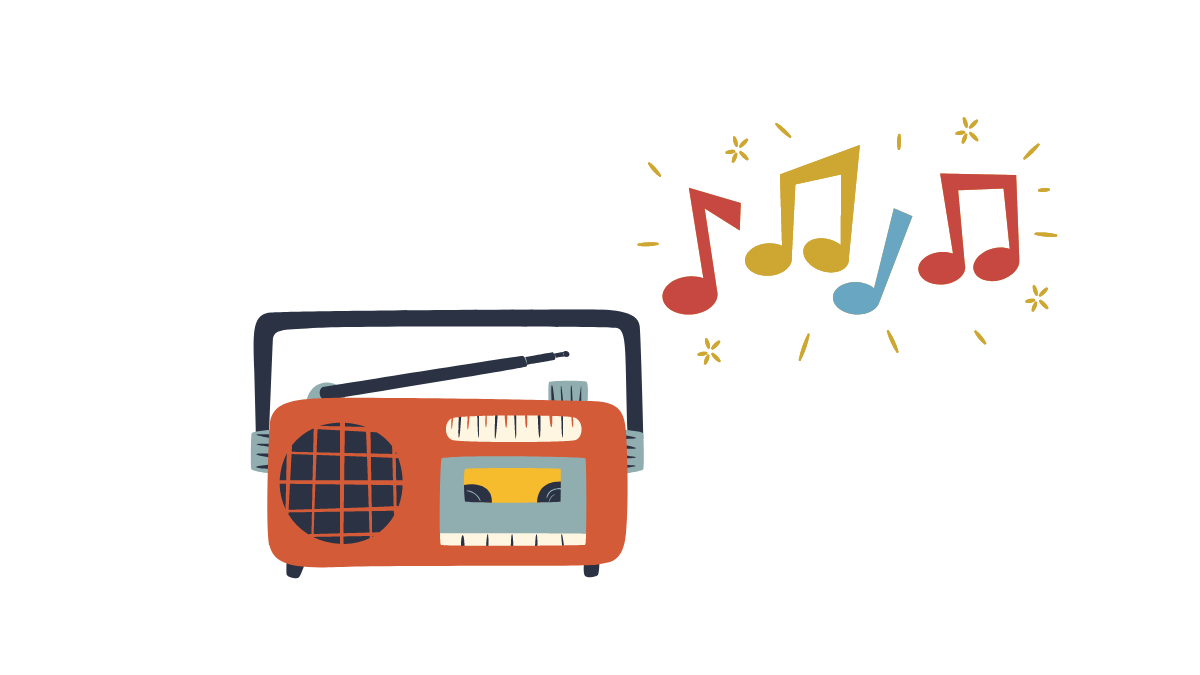
シ~ンとした中だと、リスナーはどうしてもパーソナリティのトークの"間"が気になります。
パーソナリティも緊張しちゃいます。
そこで、番組冒頭から数分間、BGMを入れてみるのをおすすめします。
不思議なことにそれだけで大分プロっぽい雰囲気。。
ずっとBGMが流れているとリスナーが耳障りに感じるかもしれないので、1曲分程度の時間で良いと思います。
同じ意味で冒頭にタイトルコールを準備しておくのもおすすめです。
タイトルコールやBGMは雑誌やウェブサイトでいうところの表紙やヘッダーのようなもので、それがあるだけで「見栄え(聞き映え?)」が違ってきます。
ずっと使えるモノなので、面倒でもぜひ準備しておくことをおすすめします。
またネットラジオでは著作権が管理された(JASRACに登録された)楽曲を勝手に利用することはできません。
なので、BGMには自作曲かフリーBGMを利用しましょう。
有名なフリーBGMサイトにはDOVA-SYNDOROMEやMusMusなどがあります。
あるいはStand FMやRadiotalkに最初から用意されているBGMを使うことも可能です。
フリーBGMではなくオリジナリティを重視したいなら、ココナラで作成依頼をするのもおすすめです。
もちろんミュージシャンなら、自分で作ってしまうのが一番良いでしょう。
初心者は2人でやるのがおすすめ
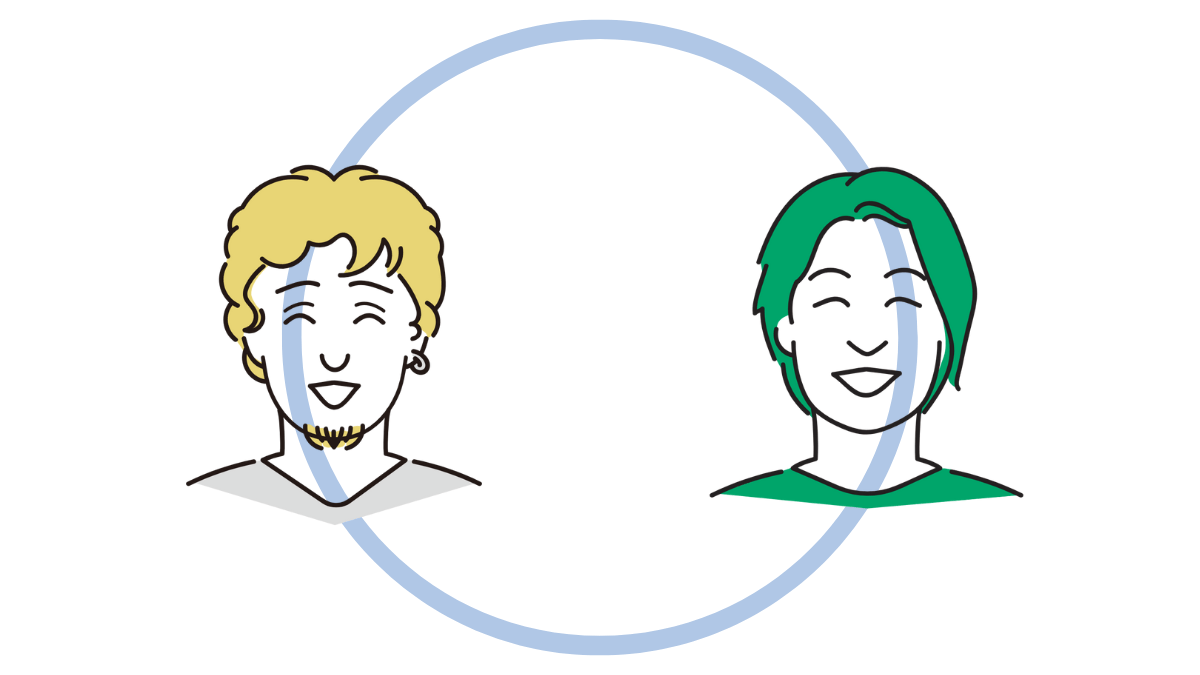
簡単そうに見えて、1人でリスナーに話し続けるというのは実に難しいです。
仮にできても「おもしろいトーク」なんてほとんどできません。
素人のネットラジオなら「すべらない話」に挑戦するより、仲の良いパートナーや仲間との楽しい空気感を伝える方が良いのではないかと思います。
もちろん、リスナーとってはおもしろい方が良いでしょうか、多分リスナーもこちらが素人だとわかって聞いてくれているはず。
ですから、まずは自分たちが楽しむことを大事にする。
継続するモチベーションもわきますし、結果的におもしろい番組になるのではないでしょうか。
逆に5人以上はおすすめできない

これは単純に誰が喋っているかわからなくなります(笑)
わたしの番組ではバンド仲間をゲストに呼んで番組作りをしていたので、最大7人の収録になったことがあります。
まぁ、そうなると1人や2人は全然喋れない人が出てきますよね(笑)
おそらく初めて聞いた方は誰が誰だかわからなかったでしょう。
これは大きな失敗でした。
しゃべらない人が出てくると意味もないので、最大4人ぐらいに考えて番組作りを進めてみて下さい。
使いまわせるトークテーマを用意する

肝心のトークの内容はズバリ、ベターなものが良いです。
わたしたちは、
- リスナーの質問に答える「おたよりのコーナー」
- 思い出のアルバムを語る「俺の一枚のコーナー」
を連載モノとしてやっていました。
特に「俺の一枚」はどんなゲストでも答えやすく、また盛り上がりやすいトークテーマでした。
月並みな企画ですが、これは大正解だったと思います。
番組のテーマに合わせて、ぜひ継続できるコーナーを1つ企画してみて下さい。
毎回の放送に統一感もでるのでおすすめです。
進行表は簡単なものでOK

あらかじめ番組の内容は決めておく必要があります。
「フリーテーマで話せ」なんてお笑い芸人しかできません!
素人には地獄です(笑)
とは言え、それほどガチガチに分刻みの番組構成を作る必要はありません。
と言うのも、ネットラジオは実質的に放送時間に制限がありません。(RadioTalkは1回12分)
トークが盛り上がったらそのまま延長して収録&放送すれば良いと思います。
YouTubeなど動画だと15分以内が最適だとか言われますが、BGMとして聞き流せるネットラジオはその限りではないはず。
50分にも及ぶ回があったのですが、意外なほどよく聞かれました。
個人のネットラジオならヘタに計算するよりも、素人ならではのアツさで自分の好きなことを語るのが良いのかもしれません。
実際に使った機材と編集のコツ
理想の収録環境は、
- 密閉した空間で
- パーソナリティ1人につき、1つのマイクを立てて
収録することです。

とは言え、プロが使うようなスタジオを個人が借りられるわけがありません。
しかし音楽のリハーサルスタジオを借りて、zoom R16のような機材を利用することで、意外なほど安く簡単に近い環境をつくることができます。
素人ならこれで必要十分な環境でしょう。
と、ご紹介していますが、実は当時のわたしたちはそこまで気が回らず、ライブの録音に使っていたこのzoom Q3を使っていました(笑)
これでもけっこうきれいな音声が収録できました。
今だったらiPhoneに接続するマイクでもっと便利なモノが販売されているので、そちらの方が良いかもしれません。
もっとも、StandFMやRadiotalkはスマホの内臓マイクを使って収録しますので他の器機や編集ソフトは必要ないです。
その他のサービスも使うにしても「できるだけ気軽に収録したい!」というのではあれば、スマホ1台でも聞き苦しくない音声を収録することは可能です。
なるべくクオリティの高い音声を収録したいという方はそれぞれ機材を準備します。
編集ソフトはProToolsやCubaseといったDAWが使えれば完璧。
本格的なソフトを持っていなくても、ラジオならPCに標準装備されているアプリで十分かもしれません。
ちなみにわたしたちの番組を編集してくれていたメンバーによると、
大概安いレコーダーってのは抜けが悪いので10khz以上を上げてみる。
あと録ってるとこがリハスタなんで不要な共振(となりの部屋のベースのブーンて音とか)を極力入れないために低域(40hzくらい)をカットする。
あとは篭って聴こえる帯域を探って(だいたい400hz〜600hz)をカット。コンプはコンプというよりは単純に音圧上げるためのマキシマイザーとして使いました。
要はただぶっ潰してあげただけ!
とのことでしたので、実際の音源と共に参考にしてみて下さい。
まとめ|ネットラジオは誰でも始められる、自分だけの発信の場
ネットラジオ(音声配信)は、今やスマホ1台からでも始められます。
わたしも最初は右も左もわからず手探りでしたが、テーマや配信方法、収録環境を少しずつ整えていくことで、自分なりの番組が形になっていきました。
失敗も含めて続けてきて思うのは、「完璧を目指すより、まず始めてしまうこと」が何より大事だということ。
1回の配信が誰かの楽しみになり、コメントやメッセージが届くたびに、マイクの向こうのリスナーの存在を実感できます。
あなたの声や経験、好きなことは、きっと誰かにとって価値あるコンテンツになります。
ぜひ挑戦してみて下さい!
関連|他にもある、音楽を宣伝する方法
個人ラジオ以外にも、ミュージシャンが自分で音楽を宣伝する方法は他にもあります。
関連記事も併せてチェックしてみて下さい。