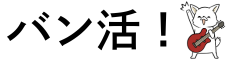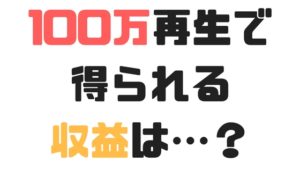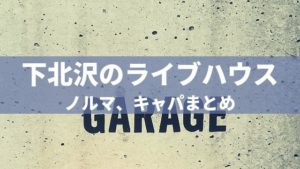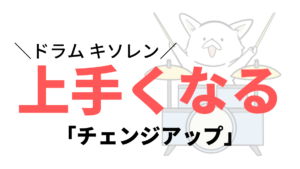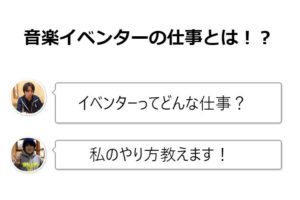Spotifyに反旗を掲げるアーティストたち。音楽配信の“次の形”を考える時

「Spotifyに死を(Death to Spotify)」──。
そんな過激なスローガンを掲げるムーブメントが、いま海外のインディーシーンで広がっています。
彼らが敵視しているのは、特定の企業ではなく、「音楽が消費されていく構造」そのもの。
ストリーミング全盛の時代に、アーティストがどんな未来を選ぶべきなのか。
この記事では、この動きの背景と、バンドマンが実践できる“次の一歩”を考えます。
Spotifyへの反旗「Death to Spotify」ムーブメントとは?
このムーブメントは、ストリーミングサービスがアーティストへ支払う印税の少なさに対する抗議から始まりました。
1再生あたり0.3円にも満たない報酬。
数万回再生されても、まともな制作費すらまかなえません。
さらにSpotify共同創業者が軍事技術企業に投資していたことが明るみに出たことで、倫理的な疑問も噴出しました。
「自分たちの音楽が、知らぬ間に戦争ビジネスに繋がるのか?」
そんな不信感がアーティストの間に広がり、「Spotifyから離れよう」という動きが生まれたのです。
これまでにもテイラー・スウィフトやニール・ヤングがSpotifyを離れた例はありますが、今回の特徴は、名もなきインディーやDIYアーティストが主導していることです。
“アルゴリズムに選ばれるかどうか”ではなく、“自分の音楽をどう届けるか”に焦点が移っているのです。
参考:「Spotifyに死を」。反旗を掲げるDIYムーブメントが世界に拡大(TABI LABO)
ストリーミングに“依存しすぎる”リスク
Spotifyなどのストリーミングサービスは、間違いなく便利で、リスナーとの最初の接点になります。
しかしそこに活動のすべてを預けると、次のような問題が起こります。
- アルゴリズムに合わなければ、いくら良い曲でも再生されない
- 作品よりも「再生数」だけが評価される
- アーティストがリスナーと直接つながる機会が失われる
つまり、「聴かれているのに、誰にも覚えられない」状態です。
これは、音楽を“消費されるデータ”にしてしまう構造そのもの。
だからこそ、海外のアーティストたちはストリーミングから一歩距離を置き、自らの手で音楽を届け直そうとしています。
「スーパーファン」モデルが示す、これからの音楽活動
こうした中で再び注目されているのが、スーパーファン(Superfan)という考え方。
そもそも先進国ではSpotifyを始めた音楽サブスクのユーザー数は頭打ちとなり、限れた市場を多くのアーティストに奪い合う現状になっています。
そこでサブスクで稼ぐことに注力するのではなく、あくまで「ファン獲得の場」として考え、別の場所でファンコミュニティを作ることが切実に求められています。
日本でも「推し活」のネーミングで、ファンコミュニティの重要性は大きくなり続けています。
1万人の“なんとなく聴く人”より、100人の“心から応援してくれる人”。
アルゴリズムや広告ではなく、人のつながりこそがアーティストの経済を支えます。
海外ではBandcampやPatreonがその基盤を担っていますが、日本でも同じ役割を果たせるサービスがあります。
あなたの「ホーム」が必要
例えば、
- BASE:音源、Tシャツ、なんでも自由に販売できるオンラインショップ。アーティスト公式ショップを5分で構築できる。
- 公式ホームページ:SNSや配信サイトの外にある“帰る場所”。作品情報や販売リンク、ライブ予定をまとめるだけでなく、メルマガやファンクラブ導線を育てることも。リスナーが「アーティスト本人の言葉」に触れられる場所として、長期的な信頼を築くため必須。
この2つを組み合わせるだけでも、アルゴリズムに頼らない自前の経済圏=スーパーファンモデルが成立します。
フォロワー数よりも、直接購入してくれる人・ライブに来る人・メールを開いてくれる人こそが、アーティストにとっての本当の資産。
インディーズバンドやアマチュアミュージシャンでも、簡単に構築・運用できるのもメリットです↓


リスナーも問われる、“支持する”という行為
「月額980円で音楽が聴き放題」。
その便利さの裏で、誰かの創作が報われなくなっているかもしれません。
Spotifyボイコットのムーブメントは、アーティストだけでなくリスナーにも問いを投げかけています。
「自分は何を支持し、どんな音楽文化を残したいのか」。
推しの曲を“聴くだけ”で終わらせず、“買う・支える”という行動に変えていく。
それがこれからの音楽シーンを守る一歩になります。
まとめ|プラットフォームに利用されず、利用する時代へ
ストリーミングやSNSの登場によって、音楽は「誰でも発信できる時代」になりました。
しかし同時に、アーティストはアルゴリズムに最適化される存在にもなってしまった。
再生数、プレイリスト、リコメンド──。
“プラットフォームに使われる”ことが、いつの間にか前提になっていませんか?
これからは、その構造を逆転させるフェーズです。
Spotifyを「使われる場」ではなく、「使いこなすツール」として捉え、自分のホーム(BASEや公式サイト)へファンを導く導線をつくる。
これからの音楽活動はあくまでファンコミュニティを育てるために、プラットフォームを利用する。
そんな”ずる賢さ”が求められるかもしれません。
その意味ではプラットフォームの攻略法も理解したうえで、戦略的に利用したほうが良いでしょう。
※例えばこちら↓


音楽活動は、再生数を競うゲームではなく、信頼を積み重ねるプロセスです。
「誰の音楽を、どこで、どう聴いてもらうか」──その主導権を取り戻すアーティストこそ、次の時代の音楽シーンを作っていく存在になるかもしれません。