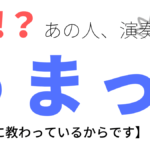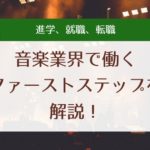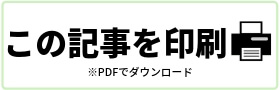意外と知られていないと思うのですが、地域の公民館で音楽ライブができるんですよね。
ただほとんどの場合、「営利目的では使用不可」だと思います。
実際のところ、営利目的の定義とは何でしょうか?
[no_toc]
公民館の営利目的の定義はかなり曖昧である
北海道の深川市でこんな事例がありました。
北海道深川市のNPO法人が昨年、市中央公民館で人形劇公演を行おうとして市教委に断られた。 「営利目的」 と判断されたからだ。
(中略)
社会教育法は、公民館で営利のみを目的とした事業を行うことを禁じている。今回のケースでは、市教委は人形劇公演を「プロ劇団による営利目的の興行」と判断し、公民館使用を認めなかった。だが、別会場での開催が決まった後、見解を一転。「広く市民に親しまれる文化活動」として実行委に助成金を出し、後援にも加わった。 市教委は 「最初は公演のチラシもなく、営利目的でないと判断する材料がなかった。営利目的とそうでないものの線引きは難しい」 と説明。今後、市や市教委が後援または助成する催しでは公民館使用を認めるという。
※太字は星川によるもの
劇やピアノ発表会、手作り品販売も許さない 深川市の公民館、使用制限しすぎ 市民に不満も
当初認められなかった公演が後になって認められることになりました。
このように公民館など公共施設を利用する際、営利目的か否かの線引きはかなりあいまいなんですね。
営利目的の定義も明確ではありません。
また、たとえ主催するコンサートの売り上げが大きくなっても、利益が小さければ良いという見解もあります。
営利として成り立っていないからですね。
公共団体が営利目的を不可とするのは、怪しい悪徳商法などを規制するためであって、市民の健全な文化活動を規制するためではありません。
例えば音楽ライブの場合、物販はダメでしょうが、i Tunesで音楽がダウンロードできるQRコードを配るのは?
次回のライブハウスでのワンマンライブの宣伝チラシを配るのは?
おそらくこのあたりの境界線は、各自治体や担当者によって違うはずです。
「公共のためのコンサート」という体裁を整えたうえで、どれだけ演者にうまみのあるライブができるか?
活動を続けるためには資金が必要ですから、大儲けはできなくても赤字を免れるぐらいの売り上げをだしたいとrこです。
ここで、合法的に公民館で入場料をとって音楽ライブをした例を紹介します。
最近見た本『0円で生きる』で興味深い発見した例です。
資料代を入場料として公民館でライブを実施した
これまで公民館のホールを無料で借りて、ロックコンサートを度々企画してきた市民団体のやり方を見てみよう。 これまでのライブでの集客は30~70人ほどという小さくない規模だ。
「コンサート」という名目で申し込み、集客してロックバンドの演奏をすることができた。ただし、入場料を取ることはできず、資料を配布して「資料代」として集金した。
また苦情が来るので音量にも制約があり、物販はできずアルコールも飲めない。時間にも厳しく、また機材のない会場ではスピーカー、アンプ、ミキサーなどを持ち込まねばならない。
こうした設備や条件は各々の自治体によって違うので、問い合わせてみるしかない。ただしそれらの機材をレンタルしても、ライブハウスでやるより安上がりだという。
資料代…!
なるほど、その手があったか!って感じですよね。(笑)
ぼくが住んでいる狛江市でも、コンサートや落語の寄席などが公民館などで度々開催されているのですが、出演者はみなアマチュアというわけではありません。
普通にプロの方も公民館でライブをやっています。
おそらくこういった名目で上手に来場者から費用を徴収しているだと思います。
趣味でも本気でも、気軽にできる公民館ライブは魅力
どれだけ些細な制約があったとしても、無料で会場を借りられるのは何物にも代えがたいメリットだ。ライブハウスなどの既存の日本の会場のシステムでは、お金がかかりすぎてしまう。これでは自由にライブを行うのは難しいのだ。
著者の鶴見さん、よくご存じで!(笑)
ライブハウスを1日レンタルすると、都内だとだいたい15万円くらいかかります。
チケット代を2000円に設定すると、75人の動員があってやっとトントンです。
公民館でのライブなら、場所のレンタル代は0円~。
ライブセット機材のレンタルも60000円程度からあるようです。

おおよそ3分の1の値段でライブができてしまうわけです。
自前で用意できる機材があればもっと安く済みそうですね。
これを3バンドぐらいで折半して、さらに「資料代」をお客さんからもらえば、金銭的なリスクがほとんどなくライブができます。
趣味でバンドをやっている人はもちろん、本気でやっている人でも「公民館ライブ」は利用価値がありますね。
音楽活動の選択肢として、ぜひ加えてみて下さい。