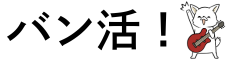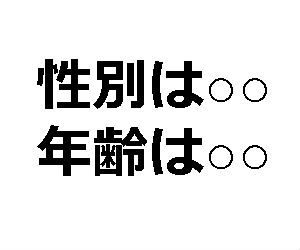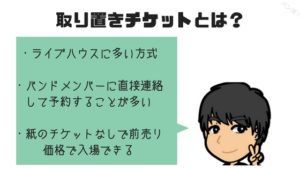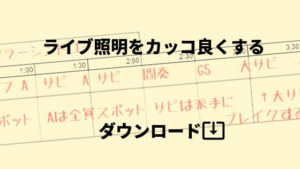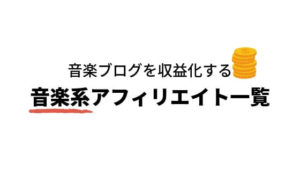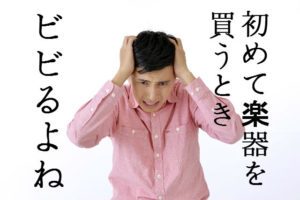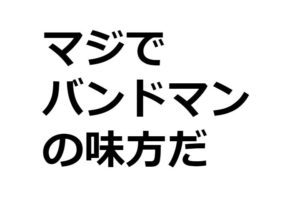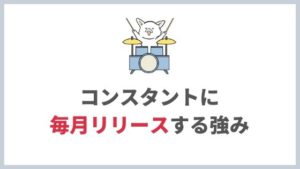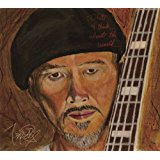個人ミュージシャンは補助金・助成金を使える?難しい現実と対策

「音楽活動に補助金・助成金が使える」と聞くと、少し意外に感じるかもしれません。
ですが、実際には国や地方自治体、財団などが支援する制度が数多く存在しています。
とはいえ、補助金制度はミュージシャンにとって使いやすいとは言いがたく、申請のハードルや事務的な負担が大きいのが現実です。
とくに個人での申請は難易度が高く、時間や労力がかかる場面も少なくありません。
それでも、条件が合えばライブイベントや海外ツアー、音源制作やMV撮影などの費用を支援してもらえる可能性があるのは魅力です。
この記事では、補助金活用の難しさもふまえたうえで、特に個人ミュージシャンが現実的に検討しやすい制度を紹介していきます。
補助金・助成金とは?音楽関連もアリ
補助金とは、国や自治体、財団などが「文化や芸術を育てたい!」という思いで用意しているお金の支援制度です。
ポイントは、返さなくていいこと。
事業報告などは必要ですが、採択されれば制作費や渡航費などの一部を支援してもらえます。
音楽活動でよく対象になるのは、ライブの開催費、機材購入、レコーディング費用、スタッフの人件費など。
意外と幅広く使えるのが特徴です。
個人ミュージシャンが申請できる代表的な補助金:アーツカウンシル
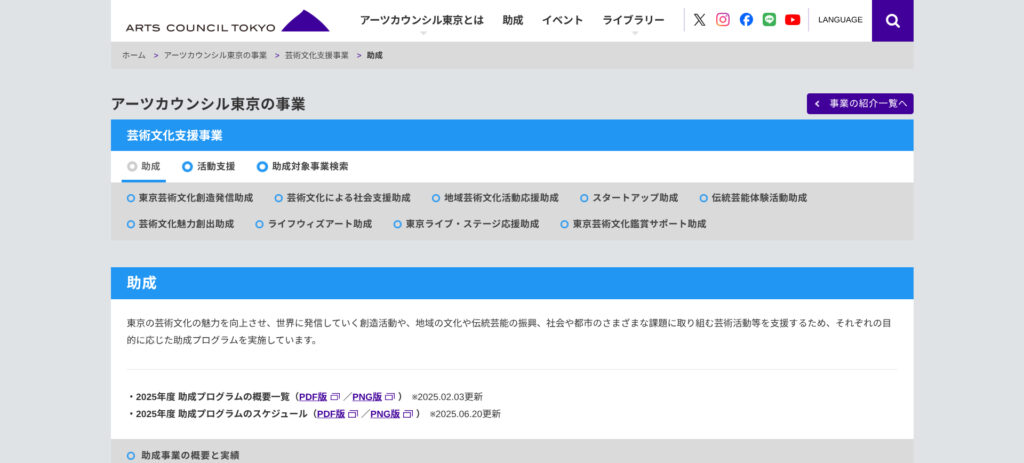
都内を拠点にする個人アーティストでも申請可能で、公演や展示、ワークショップ、教育活動などを幅広く支援してくれるのが「アーツカウンシル東京」です。
たとえば、ライブイベントの開催、ミュージックビデオの上映企画、地域連携型のプロジェクトなどにも活用できます。
主な助成制度は以下の通り。(※記事執筆時点)
| 制度名 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 東京芸術文化創造発信助成 | 公演・展示・ワークショップなど、東京都内や海外に向けた芸術活動の実施を支援 | 個人・団体ともに対象。 |
| 芸術文化による社会支援助成 | 医療・福祉・教育・地域活動などと連携した芸術活動を支援 | 市民参加型の活動向き |
| 地域芸術文化活動応援助成 | 東京の地域文化に根ざしたアートプロジェクトを支援 | 地域団体との連携が前提 |
| スタートアップ助成 | アーティストのキャリア初期の挑戦を支援する枠 | 団体:100万円 個人:30万円 かつ、助成対象経費の範囲内 |
| 伝統芸能体験活動助成 | 伝統芸能の普及や教育・体験プログラムを支援 | 邦楽・民謡・芸能系のアーティストに適用可 |
| ライフウィズアート助成 | アートを通じた生活支援、福祉・社会的包摂を目的とした活動 | 多様性をテーマにしたプロジェクト向け |
| 東京ライブ・ステージ応援助成 | ライブイベントや舞台芸術公演などを対象とした支援 | 音楽ライブも対象。会場費や制作費など |
| 東京芸術文化鑑賞サポート助成 | 高校生の芸術鑑賞機会を提供する活動を支援 | 教育機関と連携する事業に活用可能 |
申請にあたっては、活動の目的や実現可能性、社会的意義などが審査されますが、これまでにも多くのアーティストが採択されています。
またアーツカウンシルは複数の地方で展開しています。
詳しくは公式サイトをチェックしてみて下さい。
そのほかにも、個人で申請可能な補助金・助成金は存在しています。
興味がある方は以下の関連サイトをチェック。
ミュージシャンが補助金の活用が難しい理由
補助金は魅力的な制度ですが、ミュージシャンにとっては使いにくい面も少なくありません。
ここでは、その主な理由を3つ紹介します。
手続きが煩雑
補助金の申請には、企画書や予算書、実施計画など、多くの書類が必要です。
さらに、採択された後も、経費の報告や実績報告書の提出など、事務作業が続きます。
これらは本来、音楽活動に集中したい人にとっては大きな負担となりがちです。
意外と多くてどれが最適かわからない
補助金制度は国や地方、財団などさまざまな団体が実施しており、その種類も数百〜数千にのぼります。
検索しても一覧性がなく、条件もそれぞれ違うため、「どれが自分に合っているのか」がすぐに分からず、調べるだけで疲れてしまうことも。
申請期限・時期がある
補助金はいつでも申請できるわけではありません。
多くの場合、年に1〜2回の公募期間が決まっていて、その時期を逃すと次回まで待つ必要があります。
活動のタイミングと合わないことも多く、思い立ったときにすぐ使えるものではないのが実情です。
対策:ミュージシャンが補助金を活用するなら専門家・経験者に相談してみよう
補助金の制度は魅力的ですが、正直なところ「書類が大変」「報告が面倒」と感じる方も多いでしょう。
申請には、企画書や予算書、実施計画書などの提出が必要で、審査後に採択された場合でも報告義務があります。
そのため、現実的には「専門家や経験者にに相談する」ことをおすすめします。
例えば上記の関連記事で紹介した音楽イベントの企画運営に石松豊さんのサイトでは、企画書の書き方などをで紹介されています。
またココナラにて、イベント運営に関する相談を出品されています。(※記事執筆時点)
補助金・助成金だけではく、イベント運営全般の相談ができるようです。
興味ある方はチェックして下さい。
まとめ:補助金はあくまで“限定的な”選択肢
補助金は、音楽活動を広げる上でひとつの手段になるかもしれません。
ただし、誰もが簡単に使えるわけではなく、申請や報告の負担も決して軽くはありません。
個人での申請は難易度が高く、計画力や文章力、実務対応が求められます。
その分、得られるリターンも大きいですが、「なんとなく使ってみる」にはややハードルが高い制度。
あくまで補助金は“うまく使えたらラッキー”くらいのスタンスで、無理のない範囲で活用を検討してみてください。
即時的に大きな資金が必要な場合は、クラウドファンディングのほうがかえって身近かもしれません。
併せてチェックしてみて下さい。