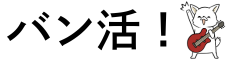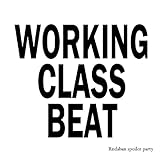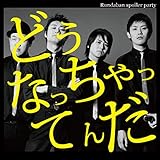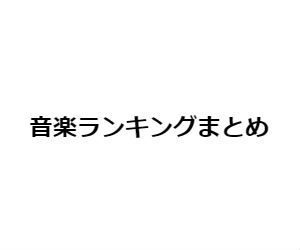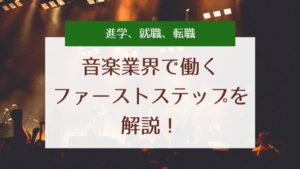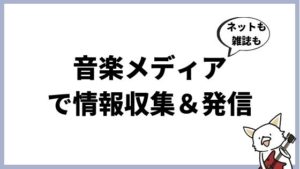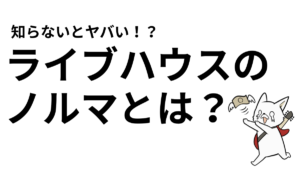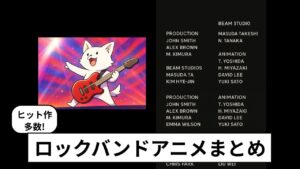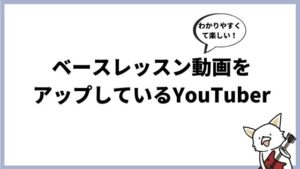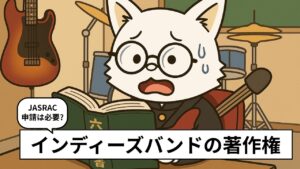歌詞の書き方|初心者は“曲先”がおすすめ。実例つきでコツを解説

「歌詞を書いてみたいけど、何から始めたらいいかわからない…」
そんな初心者の方に向けて、この記事では歌詞の書き方の基本とコツを紹介します。
わたし自身はドラマーですが、これまでに何曲も実際に作詞をしてきました。
経験上、「どうやって歌詞を作るか」は人によって違いますが、まずは“詞先”と“曲先”の2つの方法論を理解して、整理整頓しながら、詩の書き方をご紹介します。
歌詞を書く2つの方法|詞先と曲先、どっちがいい?
歌詞を書く方法には大きく分けて「詞先」と「曲先」があります。
- 詞先(しせん)
詩やフレーズを先に書いておき、あとからメロディを合わせる方法です。
ストックした言葉をもとに世界観を作りやすい反面、リズムや語感が合わないこともあります。 - 曲先(きょくせん)
先にメロディを作り、そこに歌詞をのせていく方法です。
メロディに自然にのる言葉を選びやすく、初心者にはこちらがおすすめ。
まずは鼻歌でメロディを口ずさみながら、ノリの良い言葉を探してみましょう。
歌詞の書き方|初心者におすすめの手順
ワンフレーズからふくらませる
おおむね、サビの部分でなんとなく鼻歌を歌ってみるのがコツ。
音のノリが良い言葉が見つかったら、そのフレーズを頼りにストーリーをふくらませます。
この方法だと、メロディとその雰囲気を尊重した作詞ができるのがメリットです。
例えば悲しげなメロディにやたら楽しい歌詞を乗せる…なんてミスマッチが防げます。(それが良い場合もあるのが難しいところですが)
また、初心者の場合、「その音に乗せて気持ちいい言葉」を見つけるのが、まず難しいと思います。
それなのに「テーマ」とか「メッセージ」から作詞をはじめると、頭でっかちな音楽的でない歌詞になりがち。
まずはメロディと音を尊重して、「聞いて気持ちのいい言葉」を見つけましょう。
テーマを決めてから書く
「失恋」「卒業」「青春」など、テーマを先に決めて書く方法もよく言われるやり方です。
これはどちらかといえば詞先(詩を先に書くタイプ)のアプローチ。
メリットは、あっちこっちと場面や時間軸、風景が飛び散って伝わりにくい歌詞になるのを防げること。
ワンフレーズから膨らませて、テーマをしぼろう
初心者にはワンフレーズから膨らませる方法がおすすめですが、最終的にはテーマをしぼることも大切です。
ワンフレーズから着想を得て作詞を始める場合でも、どんな感情を描くのかをひとつに絞ることで、歌詞に一貫性が出ます。
歌詞を書くときの注意点・コツ
ウソをつかない
わたしが敬愛する浅井健一さんが
カッコいいとか、キレイなことじゃなくて、本当のことを言えば良いんだよね。
という趣旨のことをインタビューで言っていたのを覚えています。
これは真実だと思っていて、作詞では「かっこいい言葉」よりも“本当の気持ち”を書いたほうがずっと心に残ります。
例えば歌詞にフィクションを描くとしても、本当は少年漫画が好きな人が少女漫画的なストーリーを描くと、なんだか薄ら寒い。
「ウソをつかない」はおそらく、もっとも大切なことです。
ワンメッセージを繰り返す
1曲に詰め込みすぎないのも大事です。
「出会い・別れ・再会・結婚」みたいな大河ドラマ的構成は3〜5分の曲では伝わりにくい。
ひとつの気持ちを繰り返し、角度を変えて描くほうが響きます。
朝・昼・晩、あるいは春夏秋冬といった時間軸。
また海・山・街といった風景。
それらも縦横無尽に描くのではなく、絞って小さな部分を掘り下げていくほうが失敗しにくいです。
韻を踏む/踏みすぎない
韻を踏むと気持ちいいけれど、日本語ではコミカルさが強く出やすいです。
とくにシリアスなテーマでは、踏みすぎると軽く聞こえてしまうことも。
言葉の響きを大切にしながらも、「踏みすぎない」バランスを意識してみましょう。
原作となる詩をたくさん書こう
曲先がおすすめとは言いつつ、良い言葉や言いたいこと・書きたいことが浮かんだら、とりあえず詩を書いておくのがおすすめです。
その詩が原作となって、よい歌詞になる場合もとても多いです。
「曲先でワンフレーズから書く」場合でも、思いついたフレーズとかつて書いていた詩の世界観がマッチして上手く歌詞が完成したり。
松任谷由実さんが、「歌詞はいつ考えているんですか?」
歌詞は常に考えている
といったことをおっしゃいたと記憶しています。
日常の中でも、心の琴線に触れた場面をなんとなくでも覚えておくこと、あるいは感受性を常に開いておくこと。
それは「詩人の習慣」とも言えることだと思います。
その意味でも「歌詞」ではなく、なにげない「詩」をひとつのネタ帳としてストックしておくのはとてもおすすめです。
歌詞の実例を紹介
最後に、実際にわたしが書いた歌詞を2つ紹介します。
ブルーカラーシンドローム
駅のホームに立って やぶれた膝に夕日が沁みるから全て
全てが真っ青に見えている帰り道に見た いたいけな女がチャリでこけた横を
素通りしてたんだ俺は全てが真っ青に見え
明日 いけるだろうか 重い荷物なぶりすてて
明日 いけるだろうか 赤い景色 燃えるだろうか駅のホームに立って 制服の男の子が
鞄を投げ出して ベンチで眠っている明日 いけるだろうか 重い荷物なぶりすてて
明日 いけるだろうか 赤い景色 燃えるだろうかこのままでここで 終わっていくか
このままでここでお前も俺たちも一緒なのだろう お前も俺たちも
全てが真っ青に見え明日 いけるだろうか 重い荷物なぶりすてて
明日 いけるだろうか 赤い景色 燃えるだろうか
とてもシンプルな歌詞ですが、これたサビの「明日 いけるだろうか」からはじめに思いついたと記憶しています。
メロディの疾走感と爽快感、フレーズが持つ焦燥感のような感情から、全体を作っていきました。
「ブルーカラー(労働者)」と「真っ青(ブルー)に見え」も言葉遊びでカケていますね。
意味を読み解くうえでは、そこが一番ポイントかもしれません。
泥棒一家
街のネオンは消え消え カラスも寝ている頃 少年たちベッドからゆっくり起き上がる
約束どおり ダマしてみせた みな親も家も置き去りにして静かに波が揺れている砂浜 今は使うことのない灯台 煉瓦街
また1人2人と集まってきてる そう今日は俺たち泥棒一家の旗揚げさ心から望んでる 心から
アジトのドアを開けたら 自由が笑ってる
ここはどこも属さない ならず者の場所さ夜の空気も冷え冷え 星たち瞬く頃 ナイフにランプを持ち寄り 準備を始めるよ
あの海の向こうに宝が眠ってる そう明日は俺たち無限の航海の始まりさ心から望んでる 心から
朝日が空を染めたら 自由が歌ってる
ここはどこも属さない ならず者の場所さ
これもサビの「アジトのドアを開けたら 自由が笑ってる」から思いつきました。
家出願望って誰しもあると思うんですね(ない?)
約束どおり ダマしてみせた みな親も家も置き去りにして
という部分が一番気に入っています。
まとめ|テーマよりも、まずは音に気持ちいい言葉を見つけよう
作詞というと「テーマを決めて」「メッセージを込めて」「語彙力を高めて」…といったことを考えがちです。
でも、初心者のうちはそれよりも「メロディにのせて気持ちいい言葉を見つけること」がいちばん大事です。
なぜなら、言葉は音楽の中でこそ意味を持つからです。
テーマを先に決めすぎると、メロディと合わずに苦しくなってしまうこともあります。
だからまずはテーマから自由になって、音に集中してみましょう。
そのうえで、最後に「どんな感情を伝えたいか」をひとつ絞る――
これが初心者が作詞を楽しむいちばんのコツです。
関連|ライブパフォーマンス向上のコツまとめ
作詞以外にも、MCや照明などライブパフォーマンスについても紹介しています。
合わせてチェックしてみて下さい。